COLUMN コラム
山下ホームの不動産お役立ちコラムです
もう散らからない!壁掛けテレビの配線&収納の正解
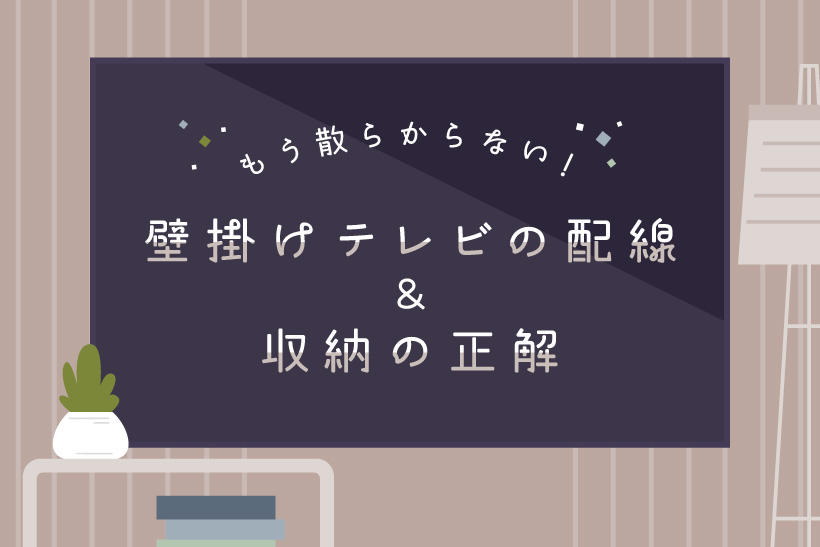
壁掛けテレビは、床から機器やコードが離れるぶん、見た目がすっきりし、掃除機やロボット掃除機もかけやすくなるのが大きな魅力です。
一方で“テレビだけ掛けた”状態だと、周辺機器やリモコン、雑誌、小さなおもちゃが徐々に集まり、せっかくの壁面が雑然として見えがち。
さらに、配線が床や家具をまたいで横切れば、ホコリのたまり場やつまずきの原因にもなります。
だからこそ、壁掛け化と同時に『まわりの収納』まで計画することが大切です。
目次
壁掛けテレビで暮らしが整う理由

定位置を決める効果
置く物の定位置、取り出しやすさ、見せる/隠すの線引きをあらかじめ決めておけば、日常のリセットが圧倒的に簡単になります。
熱・通気・交換を見据えた設計
加えて、機器の熱や通気、メンテナンス動線、将来の機種交換まで視野に入れておくと、見た目と実用が両立。
家族のリビングが長く整う“仕組み”になります。
リビング空間の最適化
本稿では、何を置くかの棚卸し、配線の目立たせない工夫、造作と市販の使い分け、見やすさの目安、安全と掃除の小さなコツまで、順を追って解説します。
もう少し踏み込むと、壁掛けは“面”の使い方を最適化する設計です。
床面に置かれる家具が減ると通路が広がり、視線も奥へ抜けます。
結果として同じ畳数でも体感的な広さが生まれ、子どもが走り回ってもぶつかりにくい。
さらに、テレビ下の埃だまりが解消され、週末の掃除が数分早く終わるという実利も見逃せません。
仕組みづくりで続けやすく
“きれいに見せる”は特別なセンスではなく、事前の計画と仕組みづくりの積み重ね。
家族みんなが無理なく続けられる収納計画こそ、壁掛けテレビを活かす鍵になります。
反対に、収納を先に作り込みすぎると“置くもの”が後追いになり、使いにくさが残りがちです。
まずは持ち物を書き出し、動線と頻度に合わせて高さと奥行きを決める——この順番が、無駄のない見た目につながります。
まず決めたいのは「何を置くか」
代表的な3グループ
はじめの一歩は、テレビまわりに『何を置き、何を置かないか』を決める棚卸しです。
典型的には、【レコーダー/ゲーム機/ルーター/外付けHDD】、【リモコンやコントローラー】、【雑誌や小物】の3グループに分かれます。
- レコーダー/ゲーム機/ルーター/外付けHDD
- リモコンやコントローラー
- 雑誌や小物
配置の工夫
使用頻度が高いものは“手の届く位置”に、配線が必要なものはテレビ近くに。これが収納設計の基本原則です。
例えばゲーム機は、電源・HDMI・LANの3本が絡みやすいため、テレビ背面または直下のボード内に置くと配線が短く整理できます。
ルーターやHDDは通気を確保しつつ、誤って抜かない高さに。
散らからない仕組み
リモコンやコントローラーは、座った姿勢で腕を伸ばさず取れる位置に浅いトレーを用意し、“投げ込み”でも整う仕組みにすると散らかりにくくなります。
雑誌や小物は見せる収納と隠す収納を混在させず、扉付きにまとめて視線を止めないのがコツ。
飾るなら“余白:飾る=7:3”程度に抑えると、テレビが主役の壁でも圧迫感が出ません。
小物はカテゴリ別にボックス化し、ラベルを日本語とアイコンの二段表記にして家族全員が迷わず戻せる仕組みに。
収納量とゾーニング
収納量は『現状+買い足し分』を見込むと、イベントや周辺機器の追加にも無理なく対応できます。
迷った物は“保留ボックス”へ。1か月動かなければ別の場所へ移し、テレビ周りに溜めないのが長続きの秘訣です。
配置の考え方としては、座った状態で腕を軽く伸ばした“ゴールデンゾーン”に日常品、
しゃがむか背伸びが必要な“サブゾーン”に予備品を置くと迷いが減ります。
充電式のコントローラーやリモコンは、USBタップをボード内に仕込み、ケーブルを短いものに統一して“絡まない充電ステーション”を用意すると散らかりません。
雑多な紙類はマガジンラックを一つだけ許可し、容量を超えたら入替える“定量管理”にすると、溜め込みを防げます。
配線を目立たせない工夫

ルートの一本化
美しい壁面を保つ最大のポイントは、配線の『ルートを一本化』することです。
方法は大きく二つ。壁内に通すか、壁表面にモールでまとめるか。
新築や大規模リフォームなら壁内配線が理想ですが、既存住宅でも白や壁色に合わせたモールで“影になる線”を作れば、視認性を大きく下げられます。
コンセント位置と余長処理
コンセント・LAN・アンテナ端子はテレビ裏に集約し、余長は裏側のケーブルマネジメントスペースでリング状に束ねると、埃だまりも減ります。
配線をテレビの中心より下に通すと影が落ちにくく、正面からの印象もすっきりします。
熱と通気の確保
もう一つの重要点が機器の熱と通気。
レコーダーやルーターは意外に発熱するため、密閉しすぎないことが故障予防につながります。
背面に数センチの逃げを設け、前扉はプッシュ式で取っ手レスにすると、開閉の度に手が当たりにくく、掃除もスムーズ。
背板にスリットや配線孔を設ければ、通気と配線の両方を確保できます。
ケーブルマネジメント
ケーブル結束はきつく縛りすぎず、メンテ時に解きやすい“ゆとり”を残すのが長続きのコツ。
電源と信号線は分けて束ねる、ACアダプタは床に置かず吊るす、などの小技も効果的です。
また、通線ルートの途中に“サービスループ”として手のひら一枚分の余長を作っておくと、機器の出し入れ時にコネクタへ負荷がかかりません。
電源系と信号系のケーブルは左右で分けて走らせ、可能なら交差は直角に。ノイズの影響を減らせます。
ラベルは端子側と機器側の両端に貼る“両面管理”にしておくと、トラブル時の切り分けが一気に早まります。
将来への備え
壁内に通す場合は、将来の規格変更に備えた通線管(PF管)や点検口を設けると安心。
屋内での小動物侵入を防ぐため、開口部は必ずキャップで塞ぎましょう。
収納の型

収納は大きく、造作ボード(フロートタイプ)と、市販ラック+壁掛けの二系統に分かれます。
【造作ボード(フロートタイプ)】
床から浮かせることでロボット掃除機が通り、見た目も軽やか。
巾木の段差を避けて壁一面にラインを通せば、空間が広く感じられます。
計画時は必ず耐荷重と下地位置を確認し、機器・書籍・引き出しの総重量を見込んでビス位置を設計。
扉はプッシュ式で取っ手レスにすると、凹凸が減って拭き掃除がラクです。
配線は内部で上下に逃がし、点検口を1箇所設けておくと機種交換がスムーズ。
棚内部は“配線スペース:収納=2:8”程度を目安に、詰め込みすぎない余白を残します。
【市販ラック+壁掛け】
機器の入れ替えが容易で、コストや納期の調整がしやすい選択肢です。
ポイントは“見せない背面”。ラックの背面で配線を束ね、壁面側に“見せないゾーン”を確保。
棚板は5mm刻み程度の可動ができるものを選ぶと、機器の高さ変更にも追随できます。
足元はコードを跨がないよう横移動の余白をとり、掃除機のノズルが通る奥行きも確保。
どちらの方式でも、家族の手が届く高さに日用品、ケーブルや予備電池はラベリングしてまとめると維持管理が一段と楽になります。
さらに、Wi-Fiの電波を遮りにくい配置や素材(背板に開口やパンチングを設ける等)に配慮すると、通信の安定性も向上します。
また、AVボードの幅はテレビ幅+左右各150〜300mmを目安に取ると、配線や装飾の逃げが確保できます。
引き戸やフラップ扉を採用する場合は、リモコンの赤外線が届くかを事前に確認し、必要ならIRリピーターを併設。
背板にはケーブル用の大径孔と、熱抜きのスリットを上下に分散して設けると内部温度の上昇を抑えられます。
フロートのクリアランスはロボット掃除機の最高点+10mmを基準にし、段差で引っかからないよう前縁を面取り。
足元の間接照明を仕込むと浮遊感が強まり、夜間の足元灯としても役立ちます。
市販ラックでは背面パネルが外せるモデルを選ぶと、模様替えや機器の増設時に作業が格段に楽です。
見やすさの目安
高さと視線
“きれいに見せる”は“見やすく視聴する”とセットで考えましょう。
目安として、画面中心の高さは床から約95〜110cm。
ソファの座面高や姿勢で前後しますが、着座したとき目線がやや下がる程度だと首が疲れにくく、壁面の抜け感も保てます。
ダイニングからも視聴する間取りなら、立位の目線との折衷で上限寄りに調整するのがコツです。
視聴距離
視聴距離は画面“高さ”の約3倍前後が目安。
4Kテレビはもう少し近づいても粗が気になりにくいため、家具配置に余裕がない場合の救いになります。
金具と調整
壁掛け金具は上下チルトや左右スイーベルに対応するタイプを選ぶと、日中の反射や作業姿勢に合わせて微調整が可能。
配線の取り回しに余長を確保しておけば、角度調整時にケーブルへ無理な力がかかりません。
実際のテスト
最後に、ソファに実際に座って“いつもの姿勢”で5分間視聴テストを行い、字幕やテロップの視認性、窓の映り込み、スピーカー位置の聞こえ方を総合判断しましょう。
音と光の条件
音と光の条件も“見やすさ”に直結します。
サウンドバーやセンタースピーカーを使うなら、画面中心と音の発生点のズレを少なく配置し、台座に滑り止めを敷いて共振を抑えるとセリフの明瞭度が上がります。
窓からの映り込みが気になる場合は、ロールスクリーンを窓枠内に納めると干渉が少なく、日中のコントラストも安定。
ダウンライトは画面の正面ではなく、視聴位置の背面〜側方に配置すると反射が減ります。
壁面が艶ありの場合は、テレビ周りだけ艶を落とすか、アクセントクロスで反射を抑えるのも有効です。
安全と掃除のコツ
地震と固定
安全とメンテ性は『最初のひと手間』が効きます。
地震対策は下地への確実な固定が最優先。
テレビ金具はメーカー推奨のボルト長で、石こうボードの場合は必ず合板下地や間柱へ。
ボードアンカーのみの固定は避けましょう。
電源とケーブル
ケーブルは抜け留め付きタップを採用し、電源の系統は高負荷機器と分けておくと安心です。
壁仕上げは凹凸の少ない素材ほど埃が拭き取りやすく、静電気による付着も抑えられます。
艶を抑えた塗装や腰壁パネルも実用的。
掃除の工夫
床置きの小物はトレー1枚に集約し、掃除の際はトレーごと移動すれば家事ラクです。
取説や保証書、予備のビスやスペーサーはクリアポケットに一式まとめ、ボード内部にフックで吊るすと、いざという時に迷いません。
最後に、配線孔の縁にはコの字カバーを装着し、ケーブルの擦れや振動音を低減。
半年に一度は背面の埃取りと結束の緩み点検をルーティン化し、ケーブルの断線や発熱、プラグの緩みを早期に発見しましょう。
子ども・ペット対策
子どもやペットがいる家庭では、ケーブルを足で引っかけない高さに配し、床上100mm程度の位置で横引きしないことが事故防止につながります。
コンセントはチャイルドロック付きプレートに交換し、たこ足配線を避けて定格内で運用。
メンテナンス習慣
掃除の運用では、ホコリが溜まりやすい“下向き端子”の差し込み部をブロワで吹き、乾いたマイクロファイバーで拭き上げる月次ルールを設定するとよいでしょう。
年1回は全機器を一時的に取り外して、配線の見直しと不要物の棚卸しを。
まとめ
壁掛けテレビを“きれいに見せる”近道は、テレビそのものではなく、まわりの収納と配線の仕組みを同時に設計することです。
何を置くかを先に決め、よく触るものは手前・配線が要るものは近く・見せたくないものは扉の中へ——この順序だけで、日々の片づけは劇的に軽くなります。
配線は壁内かモールでルートを一本化し、通気と点検の余地を残す。
収納は造作で一体感を出すか、市販ラックで柔軟性を取るか、家族の暮らし方と予算で選びましょう。
画面の高さと距離の目安、安全と掃除のミニTipsまで押さえておけば、見た目と使い勝手、メンテの三立が可能です。
大切なのは“完成形”より“続けられる仕組み”。
今日ひとつ配線を束ね、ひとつのトレーを用意するところから始めれば、リビングの印象はすぐに変わります。
最後に、将来の機器更新に備えて空きコンセントと余長、予備配管(またはモールの空きチャンネル)を残しておくと、買い替え時も壁を傷めずに対応できます。